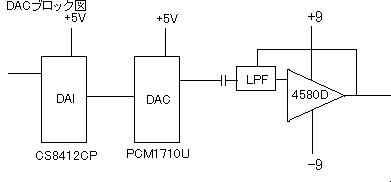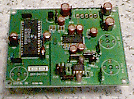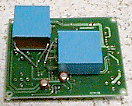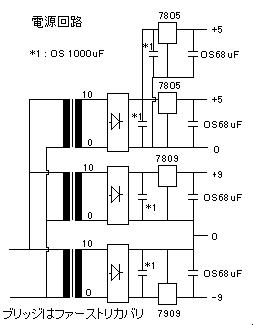2004/05/09更新
またやっちまいました・・・・電池駆動ヾ(゜◇゜)ノ
SBD+OSコン+チョークコイルの電源はそれなりに気に入っていたのですが、100均ショップで006P電池を見て、「±9VあればOPアンプなんか余裕で動作するなぁ」と思ったのが運の尽き・・・・・即効で空中配線で視聴・・・・・その差歴然!!Σ(・д・)
まだFujitsu製100均電池がどのくらい持つのか判らないけど、音の分離、静寂感、アタック全てがAC電源を凌駕してすまいますた。
電池の音を聞いた後でAC電源のを音を聞くとなんと寝惚けた音か・・・・・ヾ(T эT)〃
次はDAIとDACチップを電池駆動すんべ。
AD797でセレクター兼、ボリュームコントロール兼ラインアンプを作る気だったんだけど電池駆動を前提にせんければならんようになった。
2004/05/06更新
LPF兼バッファーのOPアンプをAD797(2個)に変更しました。
AD797は1回路OPアンプなのでゲタを作って挿してあります。
OPA2604だろうが私好みだったJRC4580DDだろうが2回路OPアンプは1回路OPアンプのAD797に惨敗でした。
ちなみにOPA627は高価過ぎて手を出せまっせん(;´д⊂)
でもAD797への換装で本DACに対する不満は解消しました。

その他の今までに実施した改造
- ブリッジダイオードをSBDに換装
- アナログ部の3端子レギュレーターを廃止
- アナログ電源ラインにチョークコイル(インダクタンス不明ジャンク品)を挿入
2004/5月現在、私のデジタル系システムは
PC→ONKYO USBオーディオプロセッサSE-U55X(コアキシャルデジタル出力)→本DAC
という構成で使用しています。
TYPE2
ラジオ技術誌で配布している基板で作ったDAC
今時は誰も見向きもしないかもしれない1bitDACを使った基板キットであります。
TYPE1でOSコンによる音の立ち上がりと鮮度の改善に気を良くして、バーブラウンの石を使っているなら
広がりや奥行きも望めるのではないかということで作ってみました。
基板と石のセットで29,000円はチョット高価ですが、まぁいっかぁ楽だし。
このキットも完売のようです。高級HiFi-DACつう10万円の基板キットはありますが、10万円ではちょっと実験に買うには高すぎます。残念!
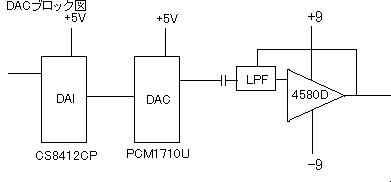
DAC部基板
- ケミコンは、全てOSコン(理由はないが今回はマルコン製)
- PCM1710Uはソケットが付属していたが基板ジカヅケ
- CS8412CPとPCM1710Uの5Vを別供給するために、基板の5Vラインをカッターで切った
- 抵抗は全て進工業
- カップリングは、ERO MKP3.3uF を基板裏に取付け
- セラミックコンデンサは、CS8412CPの電源ライン以外は入れなかった
- オペアンプの交換も実験したいため、オペアンプはソケットを取付け
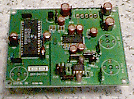 |
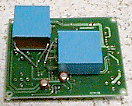 |
| 表 |
裏 |
電源部
- 安直な3端子レギュレータ
- レギュレーターは各ステージ毎に分離
- トランスは5V系と15Vを分離して3トランス
- 毒を食らわば皿までということで、一次フィルタもOSコン
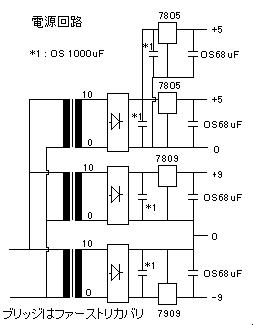
その他
 |
2000/ 3/21 トランスポートのデザインに合わせてケース交換
OSコンの被覆は取ってしまいました |
TYPE2総評
まったく予想通りで、TYPE1に広がりと低音の伸びと量が加わりました。
ただ、SPのセッティングによっては、広がりが少々不自然に聞こえる事があります。
TYPE1との低域の伸びの違いは、TYPE1がカップリングを2段もかかえているためかもしれません。
もどる