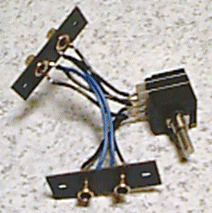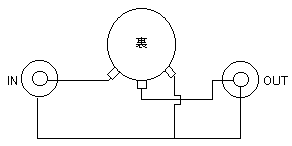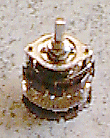音量調整用ボリュームの音質の実験
私はプリアンプを使わず、ADは金田式No.100位のTr式イコライザーと
セレクターと音量調整用ボリュームからパワーアンプにつないでいます。
今回、ボリュームの違いによる音質変化の実験をしたので書きます。
本当は、自作アッテネータが11接点しかなくて使いにくいので音の良い
VRを探そうとしたのでした。
テストは、ビンボなんで安い値段で入手できるVRだけです。
以下の4種類をテスト
- リファレンスとして2回路11接点のロータリーSWと進抵抗の自作アッテネータ(16KΩ)
- 東京光音 アッテネーター 2P2511S-G(10KΩ)
- ALPS デテント・ボリューム(10KΩ)
- COSMOS RV30YG(20KΩ)
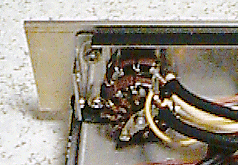 リファレンスの自作アッテネータ
リファレンスの自作アッテネータ
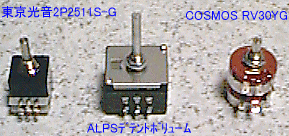 残り3種類のVR
残り3種類のVR
テスト方法
入力ピンジャックと出力ピンジャックの間に被試験VRを入れて、CDPとパワーアンプの間に入れて試聴
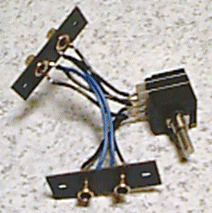
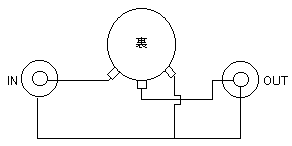
試聴結果
- 自作アッテネータ
- 東京光音2P2511S-G(10KΩ)
リファレンスと比べると、少々痩せた音がする。音場が狭くなる。
- ALPS デテント・ボリューム(10KΩ)
リファレンスと比べると、音の鮮度が少々落ちる。ほんの少し定位が悪くなる気がする。
その他は申し分ないし、リファレンスよりワイドレンジだと思う。
- COSMOS RV30YG(20KΩ)
バランスが低域により雄大な音。中高域の艶が無くなるし、シンバルが引っ込む。
私は嫌いだが、この音が好きな人がいるかも。
総評
ALPSのデテントボリュームを使おうかどうしようか迷いましたが、音の鮮度が少々落ちるのが許せなくて
結局、11接点アッテネータを使う事にしたっす。
でも自作アッテネータが無ければ迷わずALPSにしたでしょう。
そのうち、抵抗の種類による音の違い、T型アッテネータ、アクティブ・ボリュームなんてのもやってみたいっす。
でも金田教徒の私でもスケルトンのアッテネータは躊躇するな。(スケルトンは抵抗値誤差が大きいからLRのペア組み
が大変になりそう)
こうやってVRの音を聞くと、プリアンプ(パッドアンプ)なんて何の音を聞いてるのか判らなくなると思う。
1997/ 1/25追加
常用のATTが11接点では使いにくいので、セイデンの2回路22接点のロータリーSWを使って作り直しました。
でもポジションが多くなるとシリーズに入る抵抗の数が多くなり、音質劣化も激しくなるためレベル調整は15接点までで、
それ以後は使っていません。
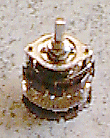 | ケースの高さの制限で小型のロータリーSWにしたため、
抵抗が重なり合って見苦しい状態になりました。 |
1997/ 3/10追加
こんなVRの案を授かったのでテストしてみました。

信号が通過するのは10KΩのスケルトン抵抗一本だし、VRは、GND間に入るので音はスケルトン抵抗に支配されて
VRの種類でほとんど音質の変化は無いのではないかと期待しましたが・・・・
やはり使うVRによって大変な音質の違いが出てしまいました。
1位:やっぱり進工業の抵抗を使ったアッテネータ
2位:COSMOS RV30YG(20KΩ)
3位:東京光音2P2511S-G(10KΩ)
4位:ALPS デテント・ボリューム(10KΩ)
という結果になりました。VRだけの時と1位以外の順位が変わってしまいました。
各VR単体で使った時より音質は良くなりますが、唯一ALPSが単体で使った時より遥かに悪く聞こえます。
現在使用している進抵抗ATTでは今回の回路で使うには抵抗値が適当ではなく作り直そうと思っていますが、
これで理想のVRに一歩近づきました。
音の良いVRを知ってたらメールください h-kaya@yk.rim.or.jp
戻る
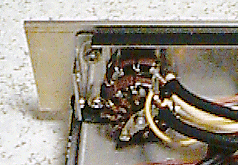 リファレンスの自作アッテネータ
リファレンスの自作アッテネータ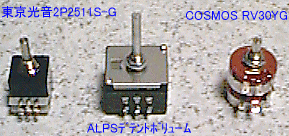 残り3種類のVR
残り3種類のVR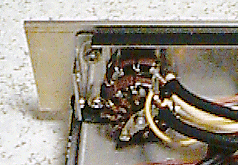 リファレンスの自作アッテネータ
リファレンスの自作アッテネータ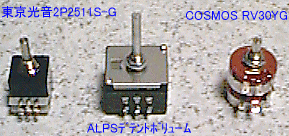 残り3種類のVR
残り3種類のVR