今回に限り(^-^;)、ピンジャック,SP端子の供回り防止のミゾも付けた。
(普段は面倒なのでピンジャック,SP端子のツメをニッパーで切ってしまう)
キャノンコネクタの20mmの穴を開けるのがチョータイヘンだった。
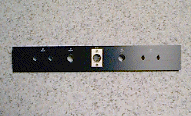 リアパネル
リアパネル
アンプ部の制作
パネルの穴空け
今回に限り(^-^;)、ピンジャック,SP端子の供回り防止のミゾも付けた。
(普段は面倒なのでピンジャック,SP端子のツメをニッパーで切ってしまう)
キャノンコネクタの20mmの穴を開けるのがチョータイヘンだった。
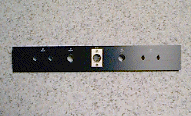 リアパネル
リアパネル
SW取付けサブパネルの作成
フロントパネルにスイッチのナットを出さないようにするため、以下のような構造にした。
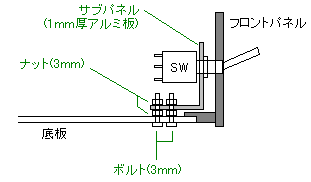
アルミ板,3mmボルト/ナットは手持ち部品
ヒートシンクの加工
ヒートシンクが横倒しで使うようにできていないため、取付け穴を開けてタップを切る。
同様に、UHC MOS-FETの取付け穴も開けてタップを切る
(UHC MOS-FET取付けは、ナットも付属しているためタップは切らなくても取付けできます)
| タップ穴:2.5mmドリル タップ切り:3mm |
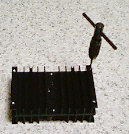 |
写真はタップを切っているところ 潤滑油を付けてやらないと タップ切りの歯が折れるょ |
FETの熱結合
熱結合してしまうとFET(K30,K117,J74)の型番の確認ができなくなるので注意!!
基板の制作
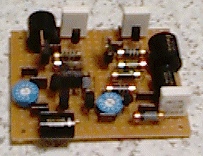 RやCの極性は下図参照
RやCの極性は下図参照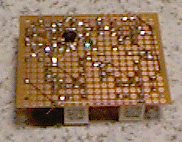 |
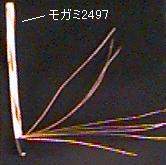 撚り線を作る 撚り線を作る |
| 各素子の極性 |
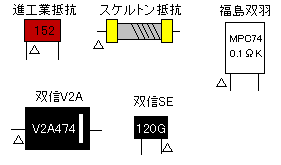 |
ケース内配線
今回は、±34VラインとUHC MOS-FETの配線はダイエイ電線30芯。
あとは、20芯で配線。
調整
電源ON時の恐怖感は何台作ってもあるっす〜
パーツセットにダミーロード用の抵抗(56Ω/5W)が14本も付いてきたが、
使わずに10Ω/10Wのセメント抵抗1本で済ませた。
トラブルは一切無く、調整は5分位で問題無く終了。その後、30分位監視した。
ただし、稼動時の再調整を心がけたほうが良いでしょう。
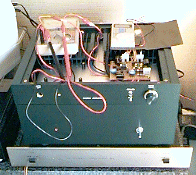 |
アイドリング電流監視用と オフセット監視用で テスター2台使用 |
パーツセット以外に必要だったもの
放熱用の穴について(1997/ 1/25追加)
熱は結構出ます。やはり放熱用の穴を開けないと不安なので天板と底板に穴を開けました。
ドライブ段のK214がかなりチンチンなので基板の真上にも穴を開けやした。
それでも、K214はかなり熱くなる。夏場は、ちと辛いかも
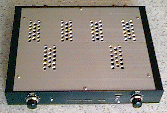
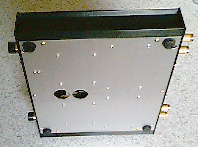
しっかしぃ、このケースのデザインは好きになれないっす。だいたい黒は好きぢゃないの。
それでいて天板が白っつうのも変!そのうち夏に向けて天板は黒のパンチングペタルに変えて、フロントパネルを白に変えたいっす。
(リアパネルは黒が正しいのでそのままが良い)
やはり、金田式アンプは究極の音と危険性が表裏一体のマニアックなアンプです。
くれぐれも過熱には注意して使うことをお勧めします。場合によっては、記事中の推奨アイドリング電流値より低めに調整したり、より大きなヒートシンクに交換する必要があるかもしれません。